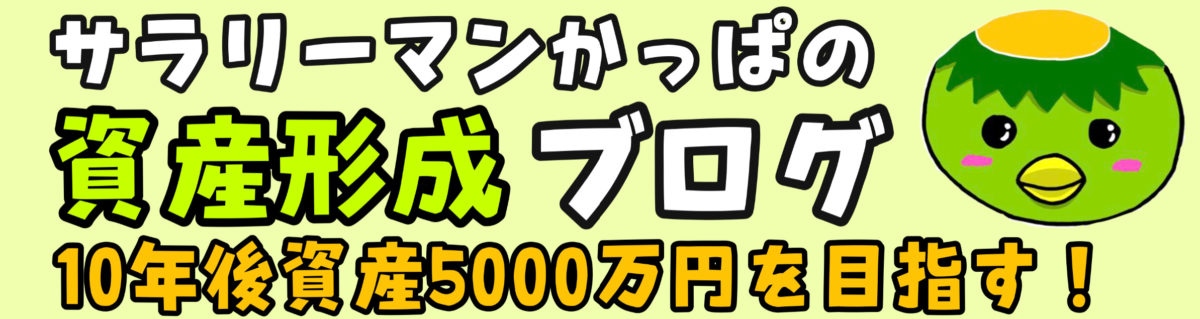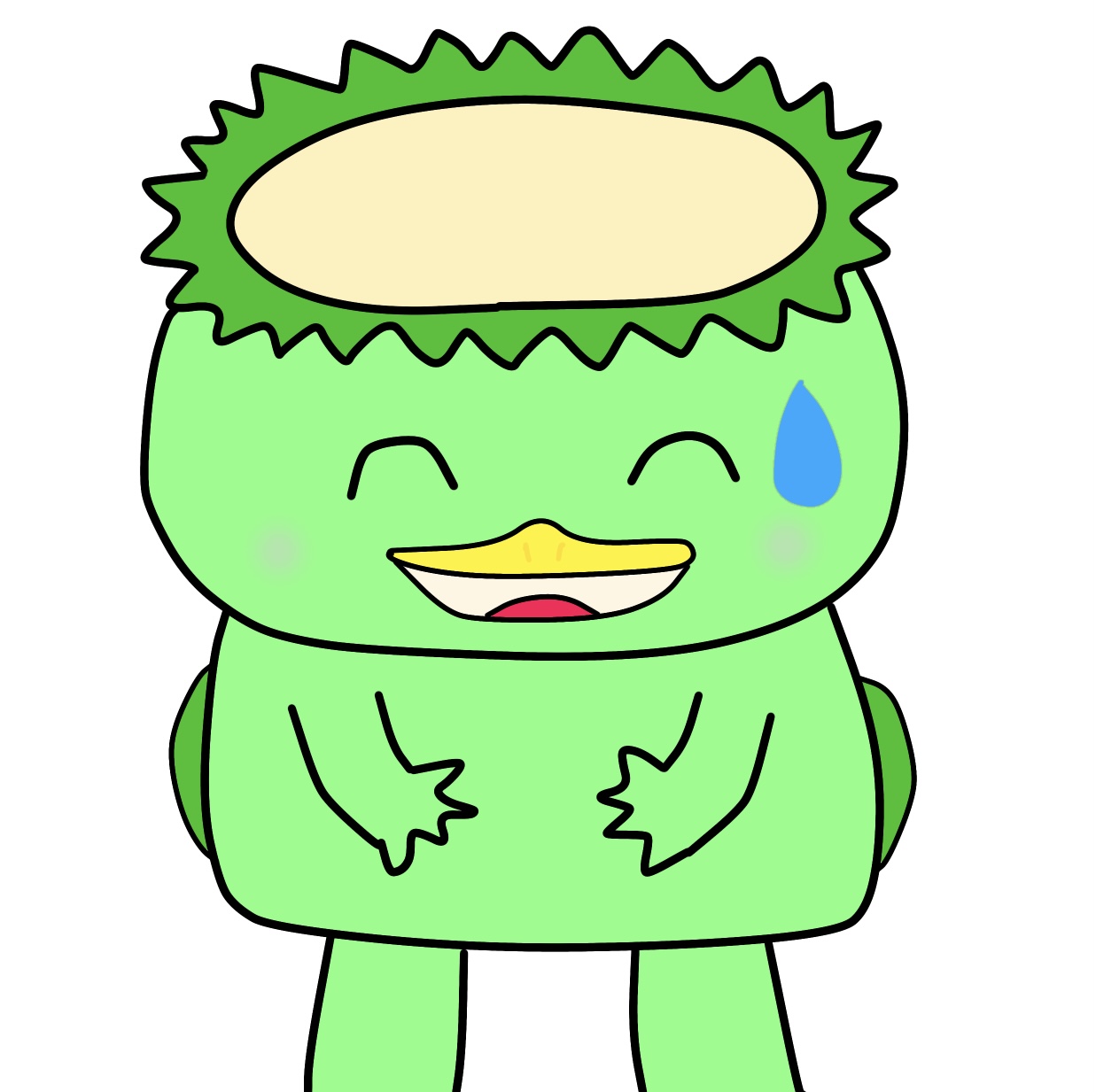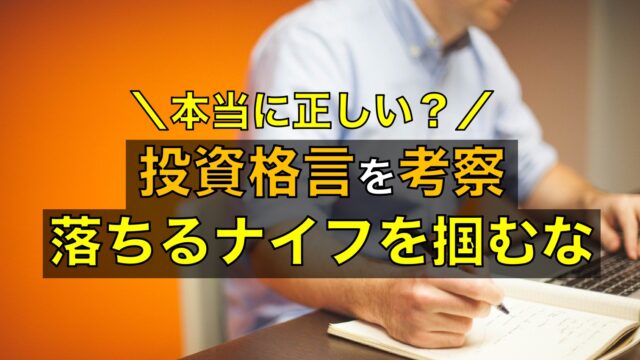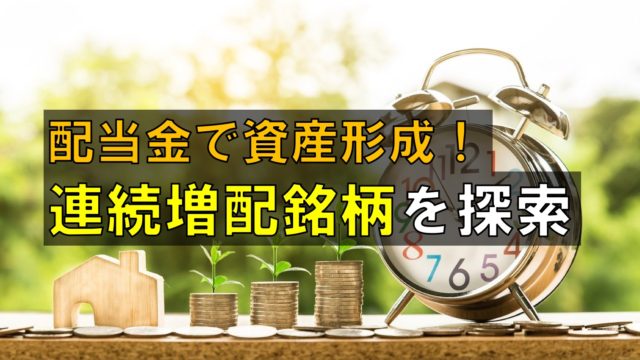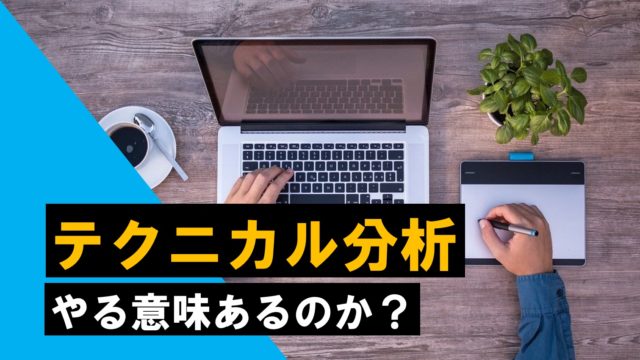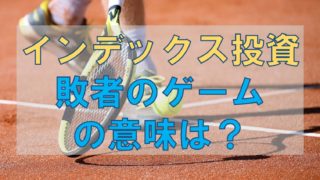株価が10倍に成長する銘柄はテンバガーと呼ばれています。野球で1試合で10本もヒットを打つという意味から生まれた言葉だそうです。
投資家であれば一度は引き当てたいと思うのがテンバガー。『一体どうやったらテンバガーに巡り会うことができるのか?』と疑問に思いませんか?
この記事ではテンバガーを探し当てるため、過去5年間でテンバガーを達成した13の銘柄についてチャート、業績、財務の推移について調査した結果をご紹介します。
- テンバガー達成の13銘柄
- 株価上昇と業績の推移
- 株価上昇と財務の推移
 配当金で資産形成をテーマに約1,500万円を運用中です。将来は不労所得で生活するために日々資産を積み上げています。Twitter(@かっぱ)もやっていますので、ぜひご覧ください。
配当金で資産形成をテーマに約1,500万円を運用中です。将来は不労所得で生活するために日々資産を積み上げています。Twitter(@かっぱ)もやっていますので、ぜひご覧ください。
【株式投資始めて6年】 毎年配当額が増えていくの楽しい 今年はどこまでいくかな? 2016年: 2,578円 2017年: 38,685円 2018年: 93,905円 2019年: 197,241円 2020年: 296,929円 2021年: 438,313円 2022年: 🤔🤔🤔🤤 pic.twitter.com/lpT0h5JUo8
— かっぱ⭐️配当金で資産形成 (@hibi_kappa) February 8, 2022
* 本記事は個人の考えを述べたものであり、特定の銘柄を推奨するようなものではありません、投資の判断はご自身でお願いいたします
コンテンツ一覧
10倍株の探し方:テンバガー13選
100万円の投資した銘柄がテンバガー達成で1,000万円、さらにその1,000万円を別銘柄に投資してテンバガーを達成すれば1億円で億り人達成です!
全くの図星です・・・まあ皮算用だとしても夢があるのでOKとしましょう!とはいえ『どんな銘柄が10倍成長するのだろう?』そんな疑問が湧いてきます。当てずっぽうに投資するにも銘柄数が多すぎます。
今回は過去5年間のチャートを確認し10倍以上の成長を達成した13銘柄を厳選しました!
過去5年のチャート、過去10年の業績と財務の推移について次の項目を確認し、テンバガーを達成する銘柄の特徴を炙り出します!ぜひご自身の目で比較してみてください!
- チャート
- 5年前の時価総額
- 1株当たり利益の推移
- 売上高の推移
- ROEの推移
- 営業利益率の推移
- 利益剰余金の推移
- 自己資本比率の推移
それではさっそく確認していきましょう!
エスプール(2471)
一つ目の銘柄はエスプール。2016年時点の時価総額は45億500万円でした。
2016年初は25円で、2020年初には950円まで上昇したので、株価は38倍上昇したことになります。2016、2017年の2年間で株価はおよそ6倍、さらに2018、2019年の2年間でおよそ7倍上昇しています。テンバガーを達成しています。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
エスプールは2012年、2015年と純利益が赤字転落しており、1株当たり利益が赤転しています。しかし2016年に再び黒転し、以降は1株当たり利益を順調に伸ばし続けています。もちろん売上高も右肩上がりとなっています。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は2015年のマイナス成長を除き、年々増加傾向にあります。2016年以降は5%を上回る営業利益率で、2020年には10.6%にまで到達しました。ROEは2016年以降30%前後と非常に高い水準を維持しています。
自己資本比率と利益剰余金の推移
利益剰余金は2016年以降、着実に蓄積されていることが確認できます。自己資本比率は2016年の28%から少しずつ上昇し、2020年は39%にまで到達しました。
2016年の黒字転換とその後の売上高の連続増収と営業利益率の改善、1株当たり利益の連続増益が、大きな株価上昇と相関する傾向にあることが分かりました。
SHIFT(3697)
2銘柄目はSHIFTです。2016年時点の時価総額は197億1135万円でした。
2016年初は680円で、2020年末には19,070円まで上昇しました。5年以内に株価が28倍上昇したことになります。2017年の夏頃から半年でおよそ4倍の株価上昇し、その後上値を少しずつ切り上げながら、2020年はおよそ2.5倍も上昇しました。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
売上高は毎年のように増収を続けており、2016年以降もその勢いは全く衰えておりません。2013年は純利益が赤字転落しており、1株当たり利益はマイナスに転じています。しかし2017年以降、1株当たり利益は大きく増益となっていることが確認できます。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は9%前後、ROEは15%前後を維持しており、特に変化の方向性はありません。
自己資本比率と利益剰余金の推移
2015年以降、自己資本比率は低下傾向でしたが、2019、2020年と再び50%を回復しています。利益剰余金は年々増加し続けており、2020年は38億円を突破しました。
2017年以降の売上高の連続増収と営業利益率の改善、1株当たり利益の連続増益が、大きな株価上昇と相関している傾向にあると分かりました。
GMOグローバルサイン(3788)
3銘柄目はGMOグローバルサインです。2016年時点の時価総額は145億2603万円でした。
2016年初は560円で、2020年10月には14,130円まで上昇しました。5年以内に株価が25倍上昇したことになります。2016年から2017年の夏にかけて株価はおよそ7倍、2020年の10ヶ月でおよそ4倍上昇しました。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2011年以降、売上高は僅かながらも連続増収となっております。1株当たり利益は2016年以降大きな増益を継続しており、2015年の28円/株から2019年の93円/株と3倍以上の成長をしています。
営業利益率とROEの推移
営業利益率とROEは上がり下がりがあるものの、2016年以降は成長を続け、営業利益率は10%を上回るまで、ROEは16%を上回るまでに成長しました。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は安定して60%前後、利益剰余金も安定した右肩上がりに蓄積しています。
2016年以降、業績面や財務面にマイナス成長は認められませんでした。2017年夏にかけての株価上昇は業績の大きな改善を反映したものとも考えられましたが、2020年の株価上昇は業績以上にテーマ性も伴った上昇とも考えられました。社内の書類・ハンコの廃止が政府発信のもと加速する中で、GMOグローバルサインの主力である『電子認証』が注目されているのも一因であるようです。
メディカル・データ・ヴィジョン(3902)
4銘柄目はメディカル・データ・ヴィジョンです。2016年時点の時価総額は246億806万円でした。
2016年初は200円で、2020年末には3,270円まで上昇しました。5年以内に株価が16倍上昇したことになります。2016年から2018年の初頭までにおよそ8倍株価上昇しました。その後株価は下落トレンドとなりましたが、2020年から再び株価が上昇し、年初から4倍しています。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2011年以降、売上高は右肩上がりの成長を続けています。1株当たりの利益は上がり下がりが認められますが、概ね成長の傾向があります。2018年12月期は子会社の事業進捗の遅れが生じたことで、利益の大幅なマイナスがありました。
営業利益率とROEの推移
前述の通り2018年は利益の大きなマイナスのために、営業利益率やROEが大きく下がっていることが確認できます。しかしながら、営業利益率については概ね右肩上がりの成長で2019年は20%を上回るところまで来ています。ROEは5〜18%の間で上下しており、2019年で13%程度です。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は安定して80%を上回っており、利益剰余金も2016年以降は年々大きく積み上がっていることが分かります。
株価と業績の関係について、2018年の業績悪化を含めて概ね相関傾向にありそうでした。2020年の株価上昇については、2019年からの業績改善に加えて、新型コロナ感染拡大の時代背景も相まって、『医療ビッグデータを活用したオンライン診療』に対するニーズが急速に高まっていることが一因となっているようです。
ラクス(3923)
5銘柄目はラクスです。2016年時点の時価総額は193億9011万円でした。
2016年初は67円で、2020年末には2,670円まで上昇しました。5年以内に株価が40倍上昇したことになります。2016年から2019年の4年間でおよそ株価が12倍上昇し、2020年にはおよそ2.7倍上昇しました。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
売上高は2011年以降、非常に綺麗な右肩上がりとなっています。1株当たり利益も右肩上がりの成長を続けており、2020年では頭打ち・減少に転じています。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は25〜20%弱と高い利益率を維持しており、ROEも15〜30%弱と高い水準を維持しています。2020年は営業利益率とROEが減少に転じています。
自己資本比率と利益剰余金の推移
2014年以降、自己資本比率は60%を上回っており安定しています。また利益剰余金は年々積み上がっていることが見て取れます。
ラクスはストックビジネスを展開しており、安定した売上を上げています。そのような理由から増収増益を継続し、株価も連動して上昇し続けたと考えられました。人手不足や働き方改革を背景として、ラクスの展開する『楽々精算』のような業務効率化とクラウドを組み合わせたソリューションのニーズの高まりも株価を後押ししていると考えられました。また7期連続増配の株主還元の姿勢も評価されているかもしれません。
田岡化学工業(4113)
6銘柄目は田岡化学工業です。2016年時点の時価総額は46億3313万円でした。
2016年初は1,190円で、2020年末には14,700円まで上昇しました。5年以内に株価が12倍上昇したことになります。綺麗な右肩上がりのチャートで、2016年から2018年の3年間でおよそ3倍の株価上昇、2019年、2020年の2年間でおよそ3倍の株価上昇しています。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
売上高は僅かながら2014年以降は連続増収となっています。1株当たり利益は2013年の6.25円/株から2020年の661円/株まで大きく右肩上がりの成長を示しています。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は2015年以降は前年比でプラス成長の傾向があり、2020年は10%を上回るところまで来ました。ROEについても2014年〜2016年で大きく成長し、以降は15%前後の水準を維持しています。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は40%前後を維持しながら少しずつ増加し、2019年には50%を上回るところまで来ました。2016年以降、利益剰余金は増加し続けています。
2016年以降の営業利益率やROEの改善と1株当たり利益の成長と相関して株価が成長してきたと考えられました。2018年以降は連続増配を継続しており、業績の成長に伴う株主還元の強化が株価成長を後押しした一因であると考えられました。
Jストリーム(4308)
7銘柄目はJストリームです。2016年時点の時価総額は37億2265万円でした。
2016年初は270円で、2020年末には6,840円まで上昇しました。5年以内に株価が25倍上昇したことになります。2016年の1年で株価は2倍に成長しました。そして2019年末から1年でおよそ13倍の株価成長を遂げました。1年でテンバガー達成です。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2015年以降、少しずつ売上高は成長しています。1株当たり利益は上がり下がりを繰り返しており安定した成長は認められておりません。
営業利益率とROEの推移
2014年以降、営業利益率は6%前後を推移しています。ROEはおよそ6%前後を推移しております。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は80%弱を推移しています。利益剰余金は2013年以降どんどん積み上がっている状況です。
2020年期までの業績面で株価上昇を説明する変化は認められませんでした。しかし現在、新型コロナウイルス感染症の対策の一環で動画利用の需要が急増している中、WEB講演会等のライブ配信の受注が急増していること、関連するWEB・映像コンテンツ制作も需要が増えてきていることから2021年期が過去最高益を更新しており、この点が評価され株価上昇につながっていると考えられました。
トリケミカル研究所(4369)
8銘柄目はトリケミカル研究所です。2016年時点の時価総額は42億902万円でした。
2016年初は490円で、2020年末には16,930円まで上昇しました。5年以内に株価が35倍上昇したことになります。2016年、2017年の2年で株価はおよそ6倍上昇し、2019年、2020年でおよそ4.5倍上昇しています。非常に綺麗な右肩上がりのチャートとなっています。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2013年以降、売上高は連続増収で2020年は2013年の2.5倍の売上高となりました。1株当たり利益は2013年の2.18円/株から2020年の376円/株まで非常に大きく成長しました
営業利益率とROEの推移
営業利益率とROEともに非常に大きく改善しています。営業利益率は2013年の1.23%から2020年の28.15%まで急成長、ROEも2013年の0.15%から2029年の32.27%まで急成長しています。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は一貫して60%前後を維持、利益剰余金は2015年以降着実に積み上がっており、財務面での健全性が伺えます。
売上高の持続的な成長、収益性の改善と成長に伴い、1株当たり利益は大きく成長しており、株価上昇と相関していると考えられました。好調な業績を背景に、配当金についても7期連続の増配実績があり、引き続き増配予定です。このような株主還元の姿勢も株価成長の一因となっているのかもしれません。
弁護士ドットコム(6027)
9銘柄目は弁護士ドットコムです。2016年時点の時価総額は173億7677万円でした。
2016年初は580円で、2020年10月には15,880円まで上昇しました。5年以内に株価が27倍上昇したことになります。2017年から2019年の3年間で、株価はおよそ7倍上昇しています。また2020年は秋口の最高値に向けて年始からおよそ2.8倍上昇しました。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2015年以降、毎年のように売上高が大きく増加していることが確認できます。また1株当たり利益も2019年の15円/株に向けて大きく成長していることが分かります。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は2016年まで大きく成長し26%を上回りました。その後低下傾向にあり、2020年では9.5%程度となっております。ROEもほぼ同様の推移を経ており、2017年に21.86%という高い水準に到達しており、その後低下傾向にあります。
自己資本比率と利益剰余金の推移
2013年以降、自己資本比率70%前後という高い水準を維持しています。利益剰余金は2015年以降に急速に積み上がってきていることが分かります。
高い利益率を背景に売上高や1株当たり利益は右肩上がりに成長してきました。それに伴い株価も右肩上がりに成長したと考えられました。また弁護士ドットコムは2015年からネット上で契約を締結できる『クラウドサイン』を展開しており、ハンコ廃止の動きに伴うクラウドサインの普及も株価上昇に大きく寄与していると考えられました。
アイ・アールジャパンホールディングス(6035)
10銘柄目はアイ・アールジャパンホールディングスです。2016年時点の時価総額は65億6838万円でした。
2016年初は280円で、2020年末には17,450円まで上昇しました。5年以内に株価が62倍上昇したことになります。2016年から3年間で株価がおよそ6倍上昇しており、その後やや株価を調整するも2019年からの2年でおよそ15倍上昇しています。凄まじい上昇チャートです。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2016年以降、売上高は前年比で成長し続けていることが分かります。1株当たりの利益も同様であり、とくに2020年の成長が大きかったことが分かります。
営業利益率とROEの推移
営業利益率とROEも2015年以降止まるところを知らず右肩上がりに成長を続けております。その推移もさることながら、営業利益率は2020年で47.2%、ROEは2020年で46.9%と非常に高い収益性があることが分かります。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は概ね70%前後であり、利益剰余金も年々増加傾向にあることが分かります。
高い収益性に裏打ちされた連続増収増益の業績に伴って株価が上昇したと考えられました。また近年『もの言う株主』による日本企業への要求や提案が増えており、日本企業にとってSR(Shreholder Relations;既存株主との信頼関係を築くための活動)の重要性が高まっています。こうした時代背景から、IRとSRに専門特化したアイ・アールジャパンホールディングスのコンサルティングサービスの需要が高まり業績につながっていると考えられました。
チャーム・ケア・コーポレーション(6062)
11銘柄目はチャーム・ケア・コーポレーションです。2016年時点の時価総額は24億2813万円でした。
2016年初は82円で、2020年末には1,386円まで上昇しました。5年以内に株価が17倍上昇したことになります。2016年から4年間で株価はおよそ15倍上昇しています。コロナショックの下げはあったものの、その後新高値を更新したという状況です。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
2011年以降、売上高は綺麗な右肩上がりの推移を示しています。2020年では2011年のおよそ5倍の売上高に成長しました。1株当たりの利益については2015年に大きく下げる場面がありましたが、その後は右肩上がりで推移し、2020年には2015年の17倍に成長しました。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は2015年に大きく落ち込みました。2016年以降は回復し、2017年以降は9%前後を推移しています。ROEについても同様で、15%〜24%を推移しています。チャーム・ケア・コーポレーションは介護事務を手がける会社で、この事業の特徴として開業当初に施設設備への投資がかかるという点が挙げられます。2015年は関東進出を果たした年で、設備への初期投資に伴い、営業利益が大きく減少したことが収益性低下の一因となっています。
自己資本比率と利益剰余金の推移
当初低かった自己資本比率ですが、年々増加し2020年では40.8%にまで到達し、年々財務の堅牢性が上がってきていると考えられました。利益剰余金についても2011年以降、毎年積み上がってきている状況です。
売上高や1株当たり利益が毎年成長している業績に連動して株価が上昇したと考えられました。高齢化が進む中で有料老人ホームの需要増加は続いており、需要増加に供給が追いついていないのが現状です。そういった時代背景により、近畿・首都圏で有料老人ホームを展開するチャーム・ケア・コーポレーションは売上高を伸ばすことができていると考えられました。一方で施設開設には初期投資が必要で、2015年の利益減少や2019年に行なった公募増資など株価低下の材料となる場合もあると考えられました。
メドピア(6095)
12銘柄目はメドピアです。2016年時点の時価総額は39億6946万円でした。
2016年初は200円で、2020年末には8,250円まで上昇しました。5年以内に株価が41倍上昇したことになります。2019年末までの4年間で株価はおよそ9倍に成長し、ほぼテンバガーとなりました。さらに2020年はおよそ4.6倍と大きく株価が上昇しました。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
売上高はほぼ毎年のように増加しており、特に2017年以降の増加が大きく目立っています。2017年はサービス受注が想定を下回ったこと、子会社の営業悪化に伴うのれんの一括償却により損失を計上しており赤字転落、1株当たり利益はマイナスとなっております。しかし2018年以降は大きく成長していることが分かります。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は2016年、2017年が5%台でしたが、2018年以降は16.7%〜20.8%と年々成長している傾向にあります。前述の通り2017年の純損益は赤字でしたが、その後のROEは13%前後を推移しております。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は上がり下がりを繰り返しておりますが概ね50%以上であり、2017年から2019年に向けて自己資本比率は増加し80%前後まで到達しました。2018年以降、利益剰余金は積み上がってきています。
2017年の赤字以降、高い営業利益率を維持しながら売上高と1株当たり利益は成長を続けてきました。このような業績と連動するように株価が上昇したと考えられました。またメディカル・データ・ヴィジョンの項で述べた通り、新型コロナウイルス感染症を背景として『オンライン診療』のように医療現場のオンライン化が加速しています。メドピアは医師への薬剤情報の提供をオンラインで支援するプラットフォームを構築しており、2020年はテーマ株としての位置付けもあったと考えられました。
レーザーテック(6920)
ラスト13銘柄目はレーザーテックです。2016年時点の時価総額は280億4573万円でした。
2016年初は250円で、2020年末には12,200円まで上昇しました。5年以内に株価が49倍上昇したことになります。2016年と2017年の2年間でおよそ5倍の株価上昇がありました。さらに2019年から2020年の2年間でおよそ9倍の株価上昇がありました。非常に綺麗な右肩上がりのチャートを示しています。
それでは次に業績と財務の推移について確認してみましょう。
売上高と1株利益の推移
売上高と1株当たり利益はまるで株価のような右肩上がりの推移を示しています。特に2017年以降に大きく成長していることが分かります。
営業利益率とROEの推移
営業利益率は30%前後を維持し続けており、2020年は35%を上回りました。ROEは右肩上がりに成長しており、2020年は27%を上回りました。非常に高い収益性を維持・成長させていることが分かります。
自己資本比率と利益剰余金の推移
自己資本比率は低下傾向にあり2020年は50%弱程度です。利益剰余金は右肩上がりに積み上がっております。
高い収益性により増収増益を継続している好業績と連動して株価が上昇したと考えられました。またレーザーテックの主力事業は『半導体関連検査装置』であり、競合他社のいないニッチな領域で成長を遂げていました(近年は競合の出現が懸念)。さらに半導体を使用している商品はその需要が落ちにくいという背景もありました(例えばスマートフォンや車載装置は新型コロナウイルスの感染拡大で販売が減少していますが、代償的にリモートワークやeコマースの需要が増加するなど、結果として半導体関連の需要は減ることがありません)。このような理由が株価上昇の一因となっていると考えられました。
さいごに
今回はテンバガーのチャートと業績・財務を調査した結果についてご紹介しました。これらの銘柄に共通する特徴として、上昇前の時価総額が非常に小さい(概ね100億円以下、大きくても300億円以下)こと、業績が右肩上がりに成長していること、そして時代的に会社が展開する事業のニーズが高まってきていることなどが挙げられました。当然の条件かもしれませんが、調査をして改めて株価上昇に必要な条件なのだろうと考えさせられました。
- 時価総額が非常に小さい
- 業績が右肩上がりに成長している
- 事業のニーズが高まってきている
僕だったらテンバガーを達成する前に手放してしまいそうですが、それはともかくテンバガー銘柄に出会ってみたいものです。以上、何か参考になれば幸いです!
過去に時価総額を調べた記事です